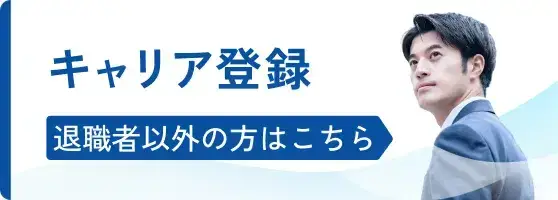工場技術者
伊藤 あずさ
2015年入社
クリーニング業務全体への理解度を深め、
工場全体のパフォーマンスを高めていく。
クリーニング事業の工場技術者としてキャリアをスタートし、現在は係長を務める伊藤あずさ。現在は主に検品を持ち場としているが、後輩やアルバイト・パートの従業員へ指導する立場にもあることから、よりクリーニング業務全体の具体的な知識を理解するための勉強を怠らない。
そんな伊藤が、工場スタッフとして働くことの魅力と面白さについて語ります。
品質を守るために
丁寧さが求められる検品業務
クリーニング工場には、担当となるエリアから、個人のお客さまのお品物が集まりクリーニング作業を実施します。工場内はフロアごとに役割が分かれていて、私の現在の持ち場は洗い作業前の工程となる検品です。検品では、ポケットにペンやお客さまの私物など洗ってはいけないものは入っていないか、ドライクリーニング非対応の品物がドライの洗い場行きになっていないかなど行き先の確認や、ボタンの素材が特殊な場合は割れてしまったり、傷がつかないように保護カバーをつける作業を行います。クリーニングのミスにつながる原因を事前に取り除くための重要な仕事で、丁寧さが求められます。

いろんな衣類にふれられることが
志望のきっかけ
入社前はファッション系の大学で、被服について学んでいました。はじめは縫製を仕事にしたいと思っていたのですがなかなか見つからず、視野を広げて考えてみたときに、さまざまな衣類にふれることができるクリーニングの仕事が魅力的に感じられたのが応募のきっかけです。
衣類メーカーだと、そこで取り扱っている服しか扱えないと思いますが、クリーニングの現場は高級な服から日常的な服まで、本当に幅広い衣類にふれる機会があります。入社以来、あらためて自分は本当に服が好きなんだと感じ、クリーニングの現場で楽しく働けています。

地道な作業のひとつひとつが
すべてつながっている
検品担当となる以前は、水洗い部門やドライ仕上げ部門も経験しました。工場業務は地道な作業が多いですが、すべては一本の道でつながっています。自分の検品が品質を守る一歩目になっていると思うと、大きなやりがいを感じますね。

クリーニングの品質を
会社全体で高めていく
お客さまの満足度向上を目的として実施している、CS委員会という会議があります。社内の各部署からメンバーが集まり、自部門・他部門問わず、それぞれの動き方をよくしていくためにはどうすればいいか、お互いにフィードバックを伝えあいます。個別では言いづらいような、部門間での「こうしてほしい」「ああすればよいのでは」といった意見を交わすことができ、ここで抽出された意見は、支店全体としてのクオリティ向上に活かされています。

ある日のスケジュール
Daily Schedule
8:00
クリーニング品の状態確認
出勤は8:00。仕事着に着替えて、検品作業を始めます。一日の大半は、持ち場での仕事となります。後工程にミスやトラブルが起きなうよう、ポケット内のものの有無、ボタンの割れや服の破れがないかなど、入念に確認します。

営業部門との情報連携
検品の際に確認事項があったクリーニング品については、営業部門に内容を申し送りし、あらためてクリーニング工程に進めるか、または返品します。正確に情報を共有することは、クリーニングの品質を高めるうえでとても重要です。

洗い場との連携
検品が済んで次工程に進めるクリーニング品を、洗い場にもっていきます。申し送り事項があるクリーニング品は、その場で直接洗い場担当のスタッフに伝え、クリーニング時に破損・汚損などが起きないよう留意します。

集計作業
夕方頃には、その日1日のクリーニング品入荷点数や、仕上げた点数を確認し、生産率を計算します。その後、機材の片付けや翌日の準備をして、17:00頃に退勤します。お疲れ様でした!

My Hakuyosha
丁寧に教えることが得意だと気がつくことができた
自分が係長の立場に就くとは、入社前はまったく想像していなかったです。
人の上に立つことは、今でもそんなに得意なつもりはありませんが、以前作業マニュアルを作り直す機会があり、その際には自分自身の成長を感じました。作業を「どのようにやるのか」だけでなく、「なぜやるのか」という理由や目的を実際に作業するスタッフにきちんと伝えていくことで、「なぜこの作業を行うのか」について納得感をもって取り組んでもらうことができるようになりました。
人に教えることが得意であることは、仕事を通じて得られた嬉しい発見でした。

白洋舍を志望する方へ一言
工場勤務は体力も必要だったり、作業自体は日々繰り返しの流れではあるのですが、だからこそ日々のちょっとした違いや、自分が少しずつ成長できる実感が生まれると思います。
丁寧な仕事・細かい仕事が好きな方や、手に職をつけたい、という考えの方にはとてもよい職場だと思います。
興味がありましたら、ぜひ応募を検討してみてください!
新卒エントリー
マイナビより
エントリーください
キャリア採用
キャリア登録フォームより
エントリーください
カムバック採用
退職者登録フォームより
エントリーください